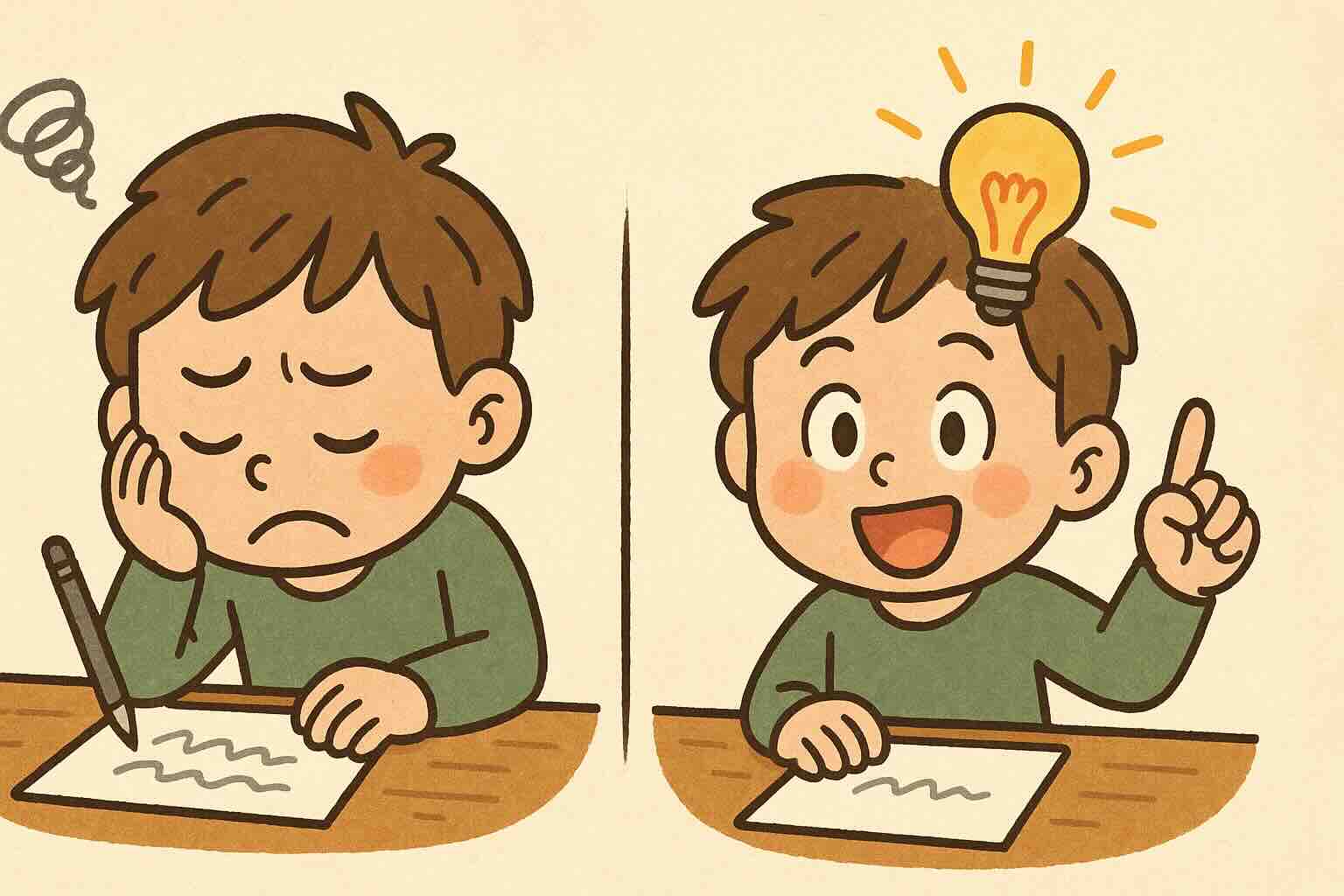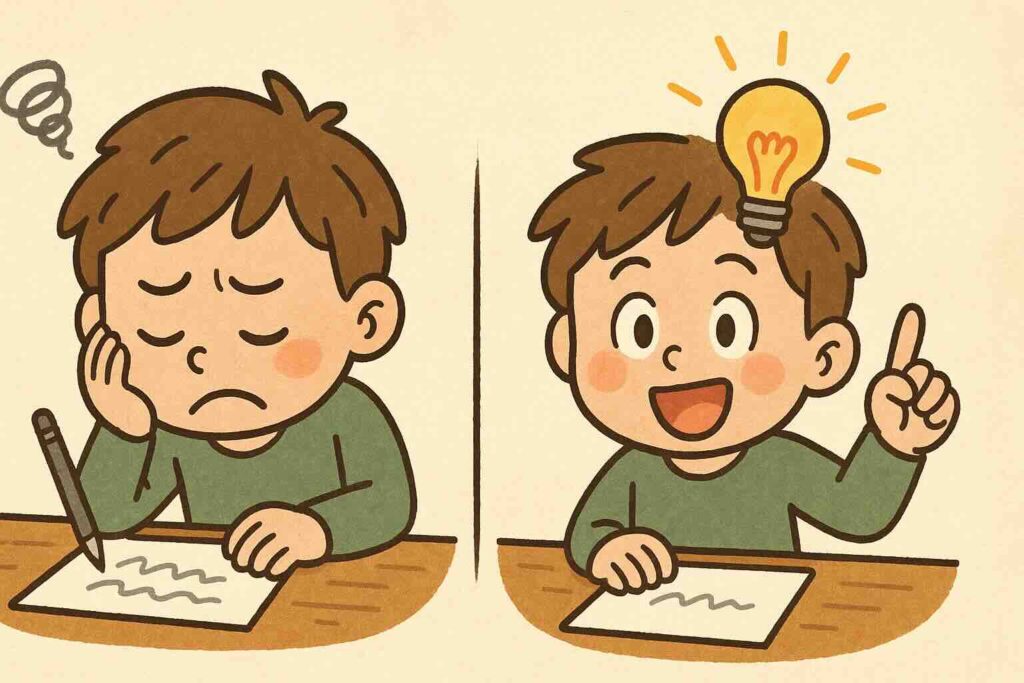
アイデアが浮かび実現できる人
探究に真剣に取り組むことは子ども達にとって大切である。その要因の第一には今後ますます「変化の激しい時代」「先が読めない時代」になることがあげられる。そのような社会に出た後、彼らが様々な状況に都度、臨機応変に対応できるようになるには、今のうちにしっかりとそのための準備と訓練をしておく必要がある。探究は、その目的に適したアプローチであり活動であるのだ——こうまとめても、多くの方は大筋に合意してくれるのではないかと思います。
ここで、臨機応変に対応するとは、状況に応じて、その状況を乗り越えるためのアイデアを出し、それを試して有効かどうか、また、その有効度合いを確認しながら、最適案を選び出していくことを指します。臨機応変という言葉からは、物事を瞬時にこなしている様子を思い浮かべますが、将来そうなれるよう、子どものうちに大いに練習を積むために、探究の時間があります。
次々とアイデアが浮かんでくる人、それを(単にアイデアに留まらせずに)形にして、問題を解決する人になって欲しいと、子ども達は期待されています。
アイデアとは
イノベーション理論のシュンペーターも、広告業界の重鎮の多くも、アイデアは既存の要素の組み合わせだと述べています。
新しい組み合わせは、今あるものの「再構成」だと呼べるでしょうが、子ども達には、その再構成とはどういうことかについて学び、それを体得してもらいたいと願います。再構成するとは、今まで使っていなかった「別のモノ」をそこに加えて新たな結び付けを試してみるということとは限りません。構成に使う一つひとつの要素自体にも再構成がありえます。要素自体のアップデートです。日常生活においてさえ、これまでの常識が見直されることは頻繁に起こります。以前は走る際に水を飲んではいけないと言われましたが、今では水分補給は当たり前です。昔、学校で教えてもらった知識が新たな発見によって見直されることもよくあります。歴史書の多くは「勝者の視点」から書かれていることが指摘されます。別の立場からなら見え方が異なるため、古書をただ素直に信じてしまってはいけないという訳です。
クリティカルに見る
したがって、一つひとつの要素を見る際にも、本当に今もそうだろうか、その後何か新しい発見がなされて人々の評価などが変わっているようなことはないだろうか、という確認が必須になります。当たり前に捉えない、鵜呑みにしないなど、懐疑的(クリティカル)な見方が大切になります。
正しく比較する
また、上述の、アイデアを一つずつ試して有効かどうか、また、その有効度合いを確認しながら、最適案を選び出していく点においては、比較が大切になります。子ども達には、正確に比較するための条件やコツを身に付けておいて欲しいと思います。その一つに、対照実験と呼ばれるものがあります。比較する点以外のことは条件を全く同等に揃えた上で行う実験のことですが、そうすることにより、その一点の影響度を計ることができます。
子ども達には、理科でも生活科でも、あるいは幼稚園の園庭活動においてでも、植物の育ち具合の違いを目にして、何が影響したのかを考える機会があります。片方には水を充分に与えなかったから、片方は日向にあって日光がよくあたっていたが、もう一方は建物の日陰になりやすいところにあったから、などです。そういった機会を捉えて、比べるということの本質を伝えていきたいものです。
私が関わってきた市場調査でも、結局のところ、価格などどれか一つの項目条件を変更して購入意向が変わるかどうかから始めて、その後に、Aという機能があってBという機能がない場合と、BがあってAがない場合であれば、あなたはどちらを選びますかといったトレードオフを繰り返していたことが多かったといえます。
やり方を知り、それを体得する
学校で教わる知識は、知に留まらず、いわば心技体の「技」にまで昇華させておかなくてはなりません。知っているだけではなく、状況に応じて使いこなせるところにまでしておくべきだということです。学校での活動は、その「技化(わざか)」を助けるものでなければなりません。
そのためには、アイデアが生まれる過程を辿り、どんなスキルが必要かをリストアップします。ヤングによれば、資料集めが一つあり、その後は「心の中で資料に手を加える」となるのですが、その「手を加える」方法も分解してみます。例えば、SCAMPERのようなものです。他には、シーン別に整理して考える方法もあります。
それから、ヤングのステップの最後の「アイデアを具体化し、展開する」にあたっても、どんな試行錯誤や確認テストを行うべきかを、身をもって知っておきます。
粘り強さが大切
結局のところ、まずは知っていることを増やし、その知っていることを抜け漏れなく順に試して行くという粘り強さが鍵になります。その粘り強さを生むにはどんな経験を積んでいることが有効でしょうか。私は、自分で決める、自分で選ぶという経験の積み重ねだと思います。そうして、自分はこうなりたいのでこれを身に付けたいと自分から言えるようになることです。身に付けるべき具体的内容は自分ではわからないことも多いでしょうから、そこには大人のアドバイスが必要です。これをやっておくといいよという推薦です。しかし、大人のやるべきことはその推薦までです。無理にやらせるところまでするのは行き過ぎです。取り入れるかどうかは本人の意思で決めてもらいます。本人の意思で決めたなら、目標が身に付いたかどうかで判断する「評価」は、人からされるものではなくなります。自身で、自分がマイルストーンを無事通過できたかどうかを知るための材料としてのみ活用されることになります。
評価との関連
総合や総探の取り組みの評価をどうしたらよいか、現場の教師は悩んでいるようです。しかし、企業人の目標管理がそうであるように、目標は、まずは本人から提示し、教師と相談して必要に応じてそれを調整するというのが本来のやり方でしょう。
自らによる目標提示も、アイデアびとになるのに必要な訓練の一つです。
10歳からわかる「まとめ」
・次々とアイデアが浮かんでくる人、それを形にして、問題を解決する人になって欲しいと、子ども達は期待されている
・アイデアは要素同士の再構成といえようが、要素自体にもアップデートという意味での再構成が求められる
・知は、知識を使いこなせるという意味での「技」にまで高めておかねばならない
・やり抜く力・粘り強さが求められるが、それを養うには目標を自分で決めるプロセスを経るのが効果的であろう

ジャートム株式会社 代表取締役
学校・企業・自治体、あらゆる人と組織の探究実践をサポート。
Inquiring Mind Saves the Planet. 探究心が地球を救う。