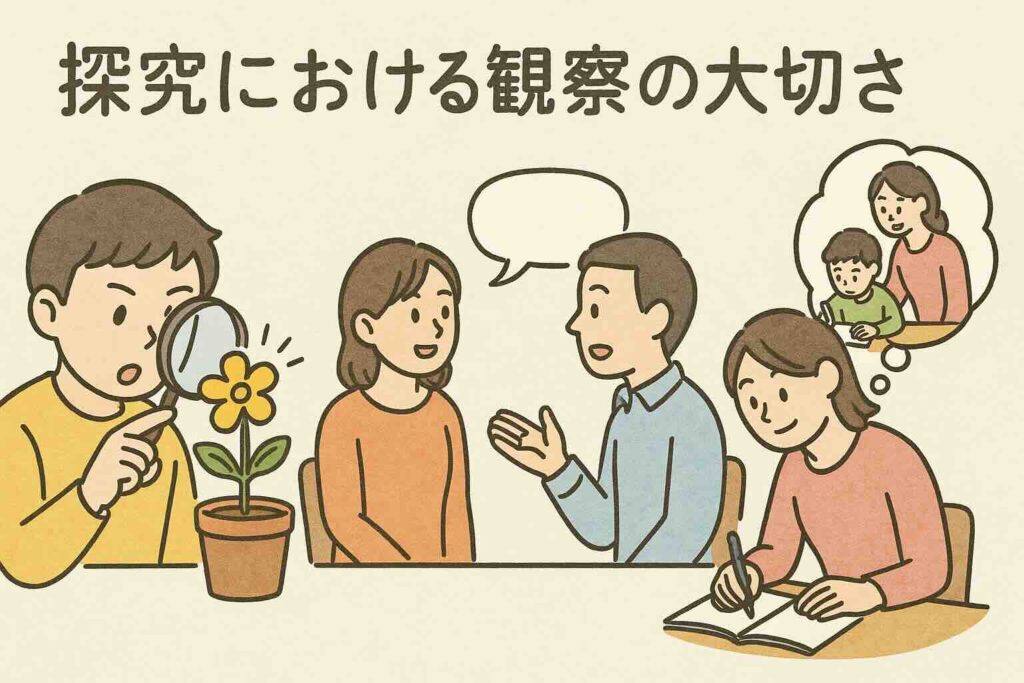
探究の中での観察
探究活動を進める中で「観察」は重要な役割を担います。調べるとなるとすぐにアンケート調査やインタビュー調査を思い浮かべてしまいがちかもしれませんが、それらの行動に飛び付く前に、まずはじっくりと現象・現状を眺める作業を組み込んで欲しいものです。それに基づく「予想立て」があると、その後の調査の質が向上します。
インタビュー前の観察
消費者リサーチを本業としインタビューを多用する中で、インタビューの実施前および実施中に行う「観察」を重視してきました。直訳すると民族誌となるエスノグラフィーは、民俗学で活用されてきた手法です。民俗学者が見知らぬ土地で現地の風俗などを研究しようとしても、言葉が通じないのですからインタビューは行えません。彼らの中に入って一緒に暮らし、ごく身近な距離から観察させてもらうことで情報収集を行います。
一方、インタビューが手法として通用する場面でも、まだ何も見ていないうちに頭だけで考えてきた質問項目をそのまま相手にぶつけては、的外れゆえに相手を戸惑わせたり、時には怒らせたりすることがあります。「こんなことも知らないでよく話を聞きに来られたな」とならないよう、事前の下調べで既存資料に目を通すのは当然のことです。加えて、現地に早めに到着し、許されるなら、少し離れたところから当日の取材対象者の仕事の様子や職場の周りの環境などを見させてもらうことは有意義な準備となります。それが、より的に近い質問を投げかけることにつながるからです。
インタビュー中の観察
インタビュー中は、まずは相手の表情を観察します。口から出てくる言葉を100%信じることはできません。嘘をつかれることももちろんありますが、それ以前に人の感情には、自身であっても、言葉で完全には説明し尽くせない部分が残ることがあるからです。とても晴れやかな表情で話しているなら、相手は、思っていることを自分でも満足できるように言葉にできているのだろうと判断できます。
この点では、以前からあった「(発言音声のみの)テープ起こし」に対しては懐疑的な捉え方をしていました。「ビデオ起こし」で、発言中の身体の動きなどを、あわせて注釈書きしてくれているものはより安心できましたが、それでも肝心な部分については、その書き起こしを手元に置きつつ、自分でもビデオを再生して見ながら反応を確認していました。現在、普及しているオンライン会議のAIによるサマリーに会議内容のサマリーとしては大きな不満はありません。しかし、インタビュー調査のケースでどの程度信頼性を見込めるのか、近々、試してみたいと考えています。
インタビュー中の観察で次に大切となるのは、こちらが用意した呈示物に対する相手の反応を探る場面です。試作品に自由に手を触れて評価してもらうような場面では、動作のスピードの変化を見落としてはいけません。次の操作が自明でないような時に手が止まるからです。そのような時は、一通り触ってもらった後の質問で、「先ほど一瞬手が止まったように感じたのですが、何かありましたか?」のようなことを尋ね、試作品の問題点の抽出に役立てます。
ところで、試作品テストで経験した「口は信用できない」には、こんなことがありました。使ってみて何か不便・不満はなかったかを尋ねた際、被験者は嘘偽りのない表情で「何もありません。とても使いやすいです」と答えました。しかし、こちらは、試用中に被験者が「わざわざ行っていること」を目にしています。今のままではその「追加動作」を解消できないため、インタビュールームの裏では、試作品の改良は必須だと、即その作戦会議が始まっていたのです。この場合の齟齬の原因は被験者が「気づいていないこと」にあります。「こんなのが欲しい」を先に言う代わりに、発明者がそれを世に出した後で、「(前から)こんなのが欲しかったのよ」と言いがちなのが人間です。相手を観察する際には、相手自らも気づいていないことまでも見て取らなくてはなりません。
観察という漢字の成り立ち
ここで、お得意の、例の「漢字つながり辞典」を使い、「観」と「察」について漢字の成り立ちを見てみます。
「観」の左側は、鸛(こうのとり)。神聖な鳥とされ、鳥を見て神意を察することから、観察の観。「みる。みきわめる」の意。
「察」の、うかんむりは祖先を祭る廟(みたまや)の屋根の形。その中で祭りを行い、神意をうかがうことを察といい、「みる」の意。
とあります。神意を「みる」ために行うのが観察ということのようですが、シンイを真意と受け取り、対象となる相手の本意・本音を見過ごさないようにしたいものです。
【参照】Web版「漢字つながり辞典」
変化の観察には記録
理科の観察には観察記録や観察日誌が必携です。昨日の様子と今日の様子を精細に比較することではじめてみえてくることがあるからです。手でじっくり書き写す作業から見えてくること、デジタルカメラで撮った写真や動画の拡大等でようやく見えてくること、両方の良さを併用しながら、観察の精度を上げていきましょう。
「観察対象が子供」のレッジョ・エミリア
イタリア発祥の幼児教育で双璧をなすのは、モンテッソーリ教育とレッジョ・エミリア教育でしょうか。一方がマリア・モンテッソーリという人の名前からに対し、他方はレッジョ・エミリアという市の名前から名付けられています。
レッジョ・エミリアの観察対象は子どもです。子どもがプロジェクトに取り組む様子を大人がノートに記録したり、動画に撮影したりして、それを活用します。活用の仕方は子ども本人との共有です。本人が写った動画を一緒に見ながら、「あなたは、この時、こんな遊びに夢中になっていたけれど、これのどこが気に入ったの?」「途中で、急に動きが変わったけれど、何かあったの?」のような問いかけをします。このやり取りの中で、子どもは振り返りができたり、自分を俯瞰できたりするわけです。言語化しようとする中で、無意識下にあった事柄に注意が向き、自分を探究する手がかりを、子ども達はそれぞれに掴んでいくのだろうと感じます。
10歳からわかる「まとめ」
・探究の過程では、観察という作業が持つ役割は重要である
・「観」も「察」も、漢字の成り立ちからは、神意をうかがう、見きわめるという意を持つ
・探究活動においては、大人は活動中の子どもの様子を観察し、記録し、それを見ながら子どもと話し合うことも有効。それによって子ども達は、自分探究に役立つ手がかりを獲得できるだろう

ジャートム株式会社 代表取締役
学校・企業・自治体、あらゆる人と組織の探究実践をサポート。
Inquiring Mind Saves the Planet. 探究心が地球を救う。


